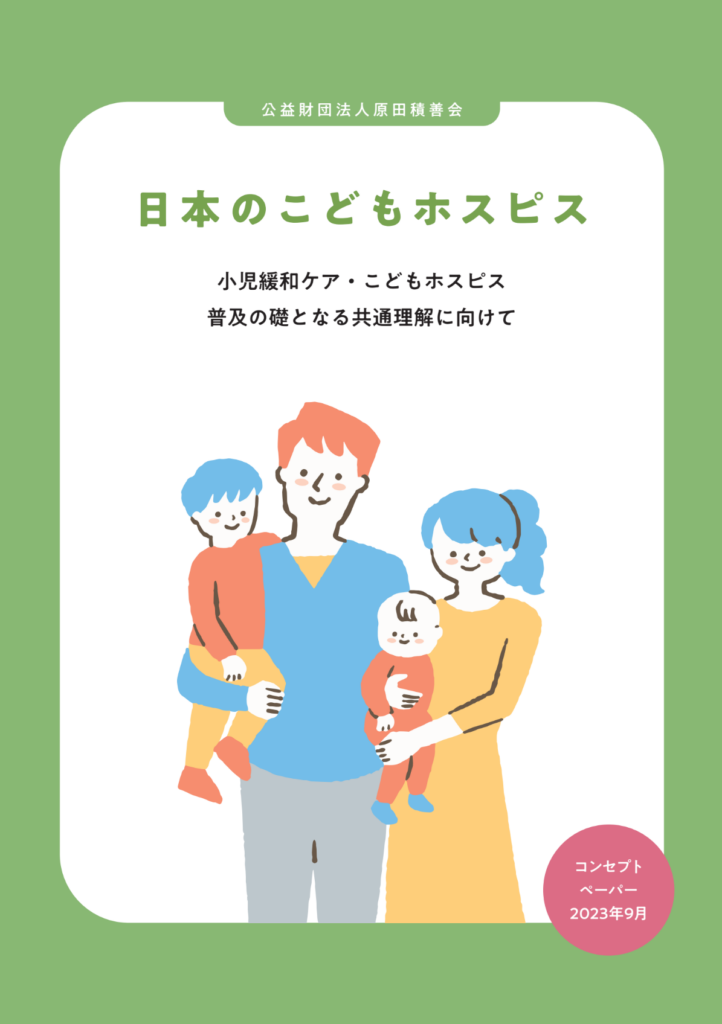すべてのこどもたちと家族に
安心と希望を

(旧 全国こどもホスピス支援協議会)
日本には、小児がん、心疾患、代謝性疾患、神経疾患など重度の疾病や障がいを抱え、生命を脅かす状態(Life-threatening conditions、LTCs)にある子どもが大勢います。そうした子どもと家族は、病院か自宅での制限された生活を余儀なくされていることが多く、子どもらしい成長・発達の機会が少ないのが現状です。また、家族も子どものケアに重点を置いた生活になり、社会的に孤立し、精神的・身体的・経済的に大きな負担を抱えています。
こどもホスピスは、治癒の見込みのない、または長期の療養が必要な疾患のある子どもと家族に、我が家のように過ごせる場を提供し、いつでも相談できる友として寄り添い、子どもだけではなく家族全体のQOL(Quality of Life)向上を目的としています。
現在、全国各地にこどもホスピス設立の動きが始まっています。
一般社団法人日本こどもホスピス協議会は、各地の事業基盤を強化し、相互に支えあい、かつ地域・社会から広く理解を得て事業を行えるようサポートする中間支援組織として設立されました。
事業内容:
- こどもホスピス関連団体の活動推進のための情報の収集・発信及び情報ネットワークの整備事業
- こどもホスピス設立・運営及びこどもホスピスにおける小児緩和ケアの人材育成事業
- こどもホスピス関連団体の支援及び国内外のネットワーク構築、並びに NPO・企業・行政等のセクターを超えたコーディネート事業
- こどもホスピス関連団体の活動推進のための調査研究、情報提供、アドボカシー、並びに普及・啓発事業
- こどもホスピス関連団体への資金的・非資金的支援
LTCのこども及びその家族の豊かな日常に寄与するため、医療・福祉・教育の縦割りではなく、「こどもと家族をまんなか」に置き、様々なステークホルダーと手を携えて、小児緩和ケアとこどもホスピスの普及を推進してまいります。
お知らせ
【第6回 全国こどもホスピスサミット in NAGOYA】開催!
<こどもホスピスを地域の誇りに:共に創る未来へ>
情熱を、社会基盤へ昇華させる。
協働(パートナーシップ)で、こどもホスピス運動を恒久的な仕組みに。
本サミットでは、全国各地で活動する団体の取り組みを共有するとともに、行政・経済界・専門家を交えた議論を通じ、こどもホスピスを社会的なインフラとして定着させるための「持続可能な仕組み」や「官民連携(パートナーシップ)」のあり方を探ります。
| 日時 | 2026年2月28日(土)14:00~17:00 |
| 会場 | ミッドランドスクエアシネマ2 SCREEN⑨(愛知県名古屋市中村区名駅4-11-27 シンフォニー豊田ビル2F) |
| オンライン | Zoomによる同時配信(ハイブリッド開催)後日招待URL配信 |
*お申し込みはこちらから(Peatix)
こどもホスピス設立講座 2025(第1期)開始します!
*お申し込み(6月30日締め切り)はこちらから
*アーカイブは公開後2週間限定で視聴可能です。
活動報告
日本のこどもホスピス
コンセプトペーパー2023年9月
こども家庭庁「令和5年度 子ども・子育て支援等推進調査研究事業」
・いわゆる「こどもホスピス」に関する国内の取組と支援体制に関する調査研究
こども家庭庁「令和6年度 子ども・子育て支援等推進調査研究事業」
こどもホスピスの役割
こどもホスピスが必要な3つの理由
1.医療では充足できない側面
医療では治療や症状管理や看取りに主眼が置かれ、子どもの「生きる時間」を充実させることは後回しになりがちです。
疾患種別や重症度、残された時間の長さに関わらず、新生児期からAYA世代などライフステージに合わせた成長・発達(遊びや学び)という子どもの権利を保障する必要があります。
2.家族支援の重要性
患児を含む家族が患児の治療のために学校や地域社会との関係性や連続性を維持することができなくなり、その経験が子どもや家族の生活に大きく影響するため、家族支援の単位とした介入が不可欠であり、既存の制度事業では行えないものです。
きょうだいと一緒に遊ぶ、季節の行事を親族と楽しむ、といった多くの子どもにとっての「当たり前」が患児には奪われてしまっている。その「当たり前」の生活を提供できる場・施設・空間として、こどもホスピスは重要な役割を果たしています。
3.医療や福祉の枠を超えたサポート
医療や福祉、教育といった「サービス」の提供だけでは不十分な「ケア」(特にスピリチュアルなケア)を、こどもホスピスは可能にします。闘病中から死別後も継続的な関わりを重視することから、死別を体験した家族・きょうだいへ支援・心の拠り所としての役割を持ちます。
子供の自己決定をはじめとする倫理的課題や、コミュニケーション等において専門的な知見・介入を行い、制度から漏れてしまう子供・家族を地域・社会で支える文化の醸成を行います。
全国に広がるこどもホスピス
会員団体
こどもホスピスのあゆみ
| 2010年 | 奈良親子レスパイトハウス発足 |
| 2012年 | 淀川キリスト教病院こどもホスピス開設 |
| 2016年 | TSURUMIこどもホスピス運営開始 国立成育医療研究センターもみじの家開所 |
| 2021年 | 横浜こどもホスピス~うみとそらのおうち開所 |
| 2022年 | 北海道「くまさんのおうち」(仮の施設として)開所 こどもホスピスを応援する議員連盟の設立 全国こどもホスピス支援協議会発足 |
| 2024年 | 一般社団法人日本こどもホスピス協議会 (旧全国こどもホスピス支援協議会)発足 |
小児緩和ケア体制整備のあゆみ
1990年から30年間で、緩和ケアは成人から小児へと展開してきました。
こどもホスピスも、広く医療施設に付随するものから、より地域に根差したものまで、各地でこどもホスピス設立の動きが広がりを見せています。
| 1990年 | 診療報酬に「緩和ケア病棟入院料」が新設がされる (対象:主として末期の悪性腫瘍又はAIDSに罹患している患者と定められた) |
| 2002年 | 「緩和ケア診療加算」創設。以後、緩和ケアチームが全国に普及 |
| 2008年 | 神奈川県立こども医療センターに日本初の子ども専用の緩和ケアチーム発足。 その後病院内で主に小児がん患者の緩和ケアを 目的とした病棟支援体制整備が進む※ |
| 2011年 | 国際基準の小児緩和ケア提供体制レベル「レベル2」認定 |
| 2012年 | がん対策推進基本計画改正で小児がんが重点項目となり、 小児がん患者への緩和ケアが政策課題として示された |
| 2013年 | 国際基準の小児緩和ケア提供体制レベル「レベル3」認定 |
| 2017年 | 小児専門病院(国立成育医療研究センター)に緩和ケア科が設立 |
| 2021年 | 医療的ケア児支援法施行: こども政策の新たな推進体制に関する基本方針が閣議決定。 「小児がん患者等が家族や友人等と安心して過ごすことが できる環境の整備の検討を進める」ことが示された |
| 2022年 | こども家庭庁設置法公布: 第4条第1項8号及び12号、第4条第2項1号の規定に基づき、 小児がん患者などが家族や友人等と 安心して過ごすことができる環境の整備にとり組んでいく |
| 2023年 | こども家庭庁設置法施行 |
※現在では大阪市立総合医療センター、大阪母子医療センター、兵庫県立こども病院、長野県立こども病院、三重大学医学部附属病院等に広がっている
わたしたち

細谷 亮太
顧問
聖路加国際病院顧問。小児血液・腫瘍学などを専門とする小児科医。1948年山形県生まれ。東北大学医学部卒業後、聖路加国際病院小児科部長、小児総合医療センター長を経て、2014年より現職。公益財団法人「そらぷちキッズキャンプ」代表理事、公益財団法人「がんの子どもを守る会」副理事長、宮城県こども病院理事も務める。著書に『医者が泣くということ』『小児がん』『今、伝えたい「いのちの言葉」』『いつもこどものかたわらに』など多数。

原 純一
代表理事
公益社団法人こどものホスピスプロジェクト副理事長・大阪市立総合医療センター顧問。1980年に大阪大学医学部を卒業後、ほぼ一貫して小児がんの研究と治療に携わっている。これまで小児白血病、横紋筋肉腫、神経芽腫の各グループで研究代表者をつとめ、現在は国立研究開発法人日本医療開発機構で小児脳腫瘍の班研究を主宰している。小児がん医療には、病院と患者支援団体の協働が欠かせないとのモットーから、公益社団法人こどものホスピスプロジェクト、NPO法人エスビューロー、認定NPO法人シャイン・オン・キッズの副理事長を併任している。

前田 浩利
理事
医療法人財団はるたか会理事長。1989年東京医科歯科大学医学部卒業後、東京医科歯科大学附属病院小児科勤務を経て1999年にあおぞら診療所を設立。その後、2011年に我が国初の小児在宅医療機関として子ども在宅クリニックあおぞら診療所墨田を開設。2013年からは医療法人財団はるたか会の理事長として、「限られた命を生きる子どもとご家族のそばで、患者さんの命と人生に責任を持って最期まで支える」という理念を実践している。『医療的ケア児・者 在宅医療マニュアル』(分担執筆、南山堂/2020年)など著書・論文多数。

田川 尚登
理事
認定NPO法人横浜こどもホスピスプロジェクト代表理事。1957年神奈川県横浜市生まれ。川崎市在住。大学卒業後印刷会社勤務。2003年NPO法人スマイルオブキッズを設立。2008年病児と家族の宿泊滞在施設リラのいえを立ち上げる。2014年こどもホスピス設立を目指すために印刷会社退職。2017年NPO法人横浜こどもホスピスプロジェクトを設立し、2021年横浜市金沢区に「横浜こどもホスピス~うみとそらのおうち」開設。他NPO法人脳腫瘍ネットワーク理事。「病気や障害がある子どもと家族の未来を変えていく」をモットーに小児緩和ケアと全国へのこどもホスピスの普及を目指している。

高橋 俊一
監事
元神奈川県職員、神奈川県横浜市西区在住。これまで、社団法人やNPO法人を対象とした補助金会計の業務に約13年間携わり、法人の皆様からの相談や、書類審査、会計事務の支援をさせていただいてまいりました。このたび監事という立場で、当法人を側面から支援できればと考えております。健全な法人の運営には、適切な会計処理はもちろんのこと、ガバナンスやコンプライアンスの強化が欠かせません。今回、監事という大切な業務を通じて、法人のチェック体制の構築に努めたいと思います。
| 組織名 | 一般社団法人日本こどもホスピス協議会 (旧 全国こどもホスピス支援協議会) Japan Children’s Hospice Association (JCHA) |
| 所在地 | 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通33関内 フューチャーセンター164 |
| 設立 | 2024年7月 |
| 役員 | 理事3名、監事1名 |
皆様からのご寄附を
お願いしております
一般社団法人日本こどもホスピス協議会
三菱UFJ銀行 横浜支店(店番 480)
普通口座:4863250
ゆうちょ銀行
普通口座:10950-31455131
<他銀行からのお振込みの場合>
店名 〇九八(ゼロキユウハチ)
店番 098
口座番号 3145513